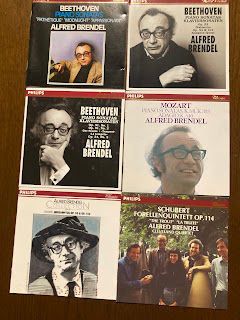NHKの朝ドラ「あんぱん」も昨日で終了。半年間楽しませてもらいました。
主人公・のぶは最後難病にかかりますが,亡くなって終わりとするのではなく,夫・たかしの尽力もあり,最後の数年間は「いきるよろこび」を持って生きることができた...といった終わり方にしていたのが良かったと思いました。「命をつないでいく」という「アンパンマン」のお話に合ったエンディングだったと思います。
というわけで,我が家に残っている,テレビアニメ「それいけ!アンパンマン」で使われていた音楽を集めたベスト盤を久しぶりに取り出してみました。「幼児はみんなアンパンマンが好き」という法則(?)どおり,我が家の子どもも大好きで,その流れで買ったものですが...30年近く前のものということに感慨を感じます。次の写真のとおり相当ボロボロです。
朝ドラの最後の方でも「アンパンマンのマーチ」は重要な役割を果たしていましたが,この曲のイントロのシンバルの鮮烈な音が聞こえると,「パッ」と画面を見てしまいますね。朝ドラの最終回前日では,「無事アニメがスタートできました」というシーンで使っていましたが,この明るい画面を見るだけで泣けてきそうになります。
 |
| 歌詞カードにはこの曲に合わせて踊る 振付けも描かれていました。 |
このベスト盤に収録されているのは次のような曲です。すべて,やなせさん自身が作詞しています。
実はアニメ自体,私自身はあまり見たことはないのですが,ばいきんまんとかドキンちゃんといったキャラクターはお馴染み。それぞれに人気がありますね。
明るいキャラクターが多い中,一味違うのがロールパンナ。ドラマでは蘭子(Rの音が共通しますね)が担当。他にも色々なキャラクターが出てきましたが,「アンパンマン」の世界観と「あんぱん」の世界観がとてもうまく重なり合っていた(誰が誰のイメージか探すのも)のも面白かったと思います。
それにしても蘭子役の河合優実さんは良かったですね。助演女優賞だったと思います。何とも言えない「冷めているような燃えているような感じ」「昭和の感じ」は,妻夫木さんの抑えた演技ともども,ドラマ全体の中で明るいアンパンマンの世界の対旋律のようにずっと続いており,それが「見応え」を作っていました。
そして今田美桜さん。ドラマの最後に行くほどドキンちゃんに顔つきが似てきたように感じてしまいました。ちなみに次の「私はドキンちゃん」は,いずみたくさんの作曲です。
好むと好まざるに関わらず,色々な人たちが重なり合い,つながり合い,時にはアンパンパンのようなヒーローに救ってもらいながら,結構生きるのが大変な人生を生き抜いていく。ある意味メルヘンの世界なのかもしれませんが,その世界観は多くの人にとって,生きる力になっていると改めて感じさせてくれるドラマでした。